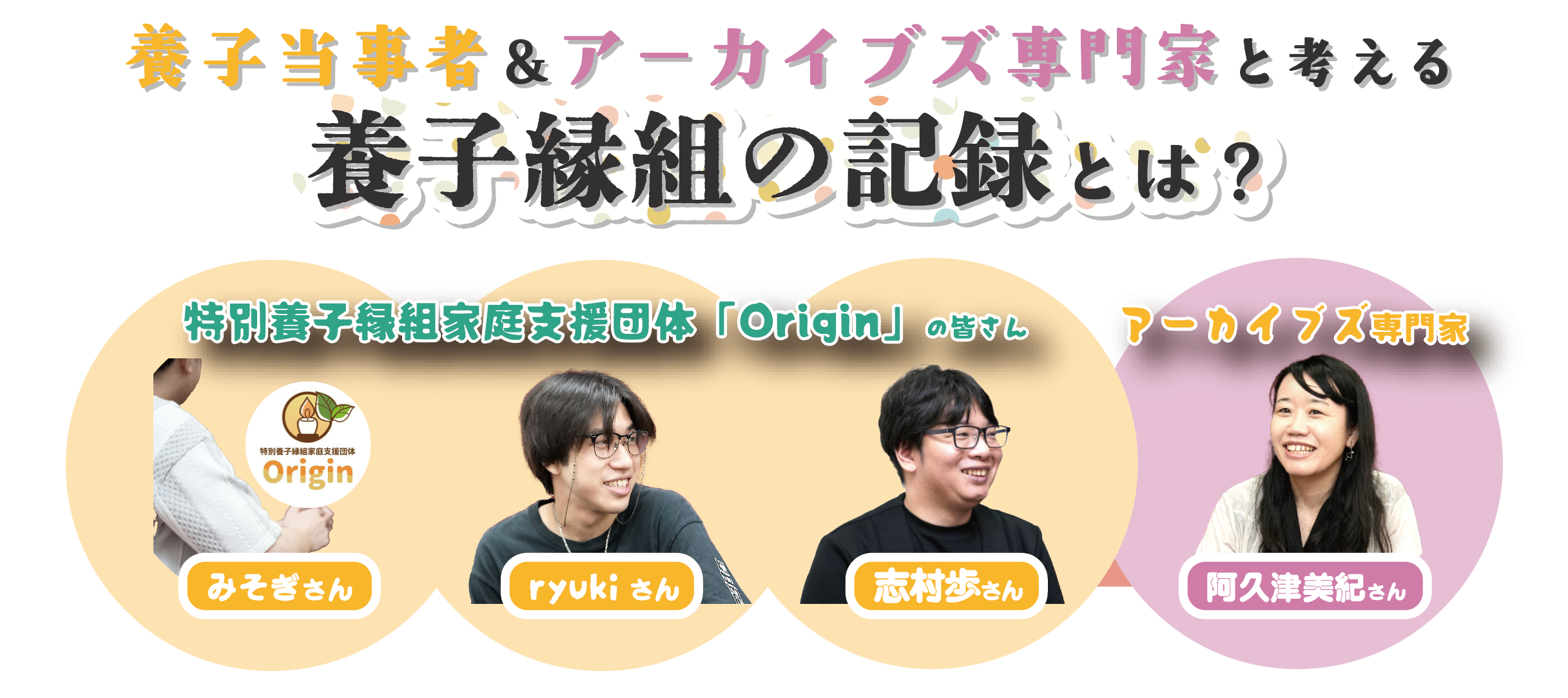
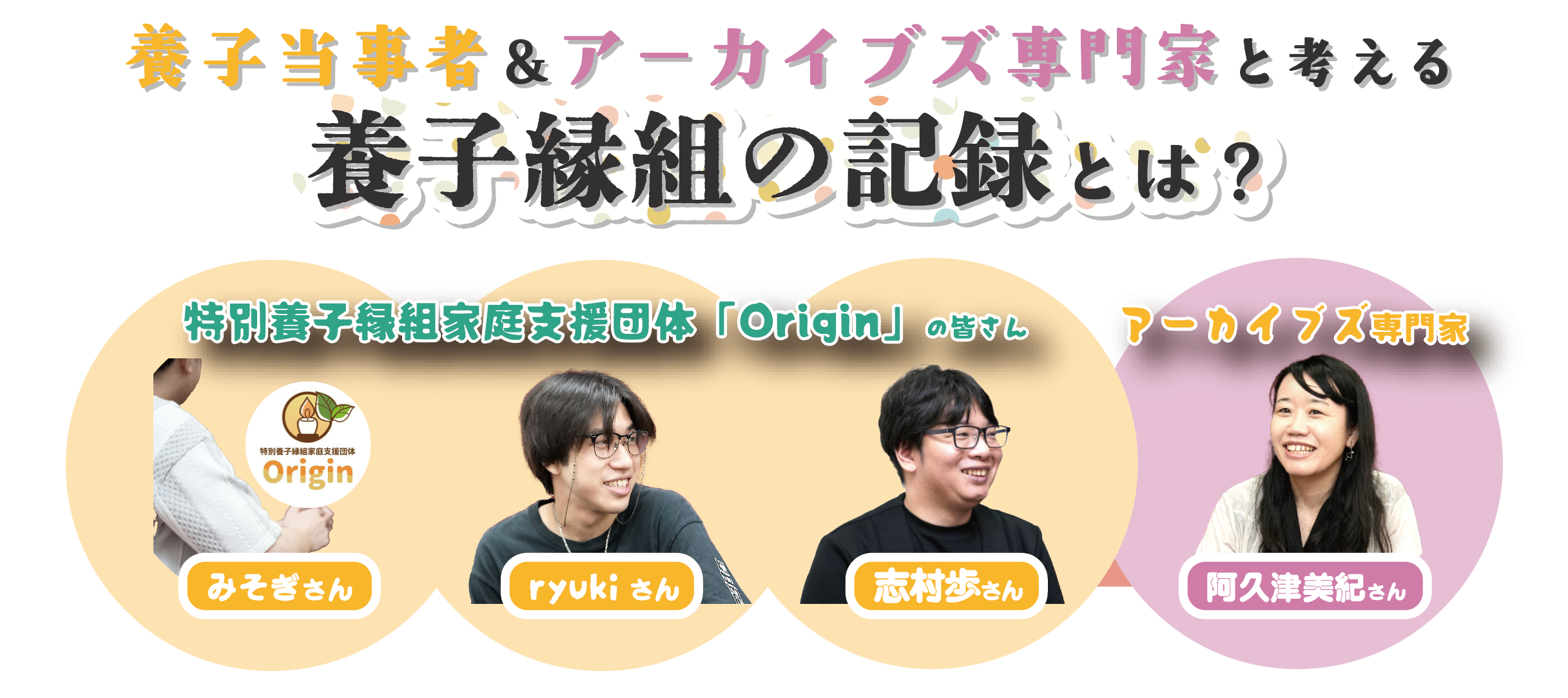
養子縁組当事者のために残される「記録」は、その保管方法もさまざまで統一されていないのが現状。
今後の課題、行政や民間あっせん機関はどうあるべきかなど、当事者たちのリアルな声をお届けします。
参加者のプロフィール

特別養子縁組家庭支援団体 Origin
特別養子縁組の当事者団体。 当事者同士のつながりづくりや出自をたどったり、気もちを整理したりするサポートや、特別養子縁組家庭の養親さんに向けた情報発信をしている。
Origin44チャンネル by 一般社団法人Origin
Xアカウント
公式ウェブサイト

阿久津 美紀(あくつ みき)氏
社会的養育や特別養子縁組に関する記録や情報管理、記録へのアクセスについて研究を行う。著書『私の記録、家族の記憶ーケアリーヴァーと社会的養護のこれから』。2024年より立命館大学衣笠総合研究機構専門研究員
まず、皆さんが出自に関して興味を持つようになったのはいつ頃でしょうか
ryuki

僕は小さな頃からずっと親(養親)から聞かされていたので、養子っていうのは知ってたんですけど、10代の思春期の頃に自分はどうやって生まれてきたんだろうということに関心を持ったんです。それで、自分のあっせん団体に手紙を書こうとしていたら、あるとき父親に呼ばれて、まだ聞かされていなかった事実を知りました。
志村

僕の場合は自分ではあまり関心がなかったのですが、興味を持たされたって感じですかね。中3か高1のときに、あっせん団体から「生みの親に手紙を書いてみてはどうか」と提案されて。それで、手紙を送ってみたところ、弟がいるということがわかったんです。でも自分の中では納得がいかず、生みの親は僕のことは捨てたのに弟は育てるのか、という葛藤が生まれました。だから僕的には思春期という多感な時期に手紙を書かせるのはどうなのか、と思いますけどね。
阿久津

それはどういう方針でおこなっているのでしょうか。あっせん団体の方針なのか、どなたかが願っているから書いてほしいということだったのか。
志村

僕の場合は、生みの親がうちの両親に直接会って「この子をお願いします」って託したんです。だから、もしかしたらそのときに生みの親に何か言われたのかなと思います。最近でも父親は、「生み母さんとコンタクトをとるように」と言ってきますから。
ryuki

うちもよく手紙書けって言われますね。
全員
へーそうなんだ!
志村

コンタクトは取っておいた方がいいと思うんですよね。僕の知り合いは30歳になってようやく気持ちの整理がついて、生み母に会いたいと思って探したら亡くなっていたことがわかりショックを受けていました。その人から直接「君ももしその気持ちがあれば会っておいたほうがいいよ」と言われて、お互いに歳をとるのでまぁ確かになと思いました。
みそぎ

僕は真実告知が遅かったので出自について考えはじめたのは大学生になってからですね。僕の養親の父(おじいちゃん)は62歳で亡くなって、父がその年に近づくにつれて気弱になっていく様子をみていて「あぁ実の親もいずれは死ぬんだな」と感じたんです。で、そのときに生みの親の生死を知りたいなと思いました。命がけで産んでくれたことは感謝して、もし亡くなっているなら、せめてお墓参りくらいは行くべきなんじゃないかと思ったんです。
阿久津

けっこうみなさん若いうちにそういう風に思われたんですね。というのは私は施設からアメリカに養子に行った人からルーツ探しを頼まれるのですが、そういう人たちは60歳前後が多く、現地の家族と一緒に来日されます。とにかく存命かどうかを確認すればよく、お墓でもいいからとか、本籍地にいってその土地の写真を撮るだけで満足されたりします。
みそぎ

SNSもあるし、物理的な移動もそこまで大変ではないという時代だから。大変だと思ってあきらめることも少ないのでは?
阿久津

まわりにもそういう方はいらっしゃいますか?
志村

結婚とか出産とか人生の転換期に考える人はいますね。女性の例ですが、結婚をする際に生みの親にどういう人と付き合って自分を産んだのかというのを聞き出して。自分の恋愛観に当てはめてみるのかなと思います。
みそぎ

僕のSNSのDMにも「どうやって探したらいいですか?」という質問はきます。大学で一人暮らしを始めたタイミングとか。ただ、最後までいかないケースが多いんですよ。たいがい途中から自分のいまの環境のことに忙しくなってしまうので。就職や結婚、養母との関係のほうが大事ですしね。こちらがどうやって辿ったらいいと教えてあげても余裕がなくなってしまって、戸籍だけ取ってあとはほっぽり出してしまうとか。そういう意味でも身軽に動ける若いうちのほうが探しやすいと思います。
「記録」に関して、どんなものを持っていますか?
ryuki

うちは養親がなんでもとってあって。母子手帳まで二冊あるんです。1冊は行政に返さなきゃいけないらしいんですけど粘りまくって手に入れたらしくて(笑)。あと裁判記録やあっせん団体とのやり取りの書類、写真、手紙、とにかく自分に関するものは全部養親が保管しています。
阿久津

それを一つ一つ全部ご覧になっているんですか?
ryuki

見てはいるんですが、そんなに深いことを考えずに「へー」ぐらいな感じで。
志村

じゃあ眺めてるって感じだね。
阿久津

本当にたくさん持ってらっしゃいますよね。

ryuki

母親がそういう真面目な性格だったのかな。
志村

うちもちゃんと取ってあるみたいですけど僕自身が見せてくれと養親に頼んだことはないです。それに自分で戸籍謄本を手に入れたので、いまはこの中の情報でけっこう満足しています。あれ?生みの親の名前は聞いたのと違うぞ、というのもわかったり。個人的には調査報告書は見たいという気持ちはあんまりないんです。どうせろくなことは書いてないだろうなって思っちゃって。
ryuki

けっこう面白かったですよ。
志村

へ~面白かった?
ryuki

うん、面白かった。生みの親が魚屋でアルバイトをしてるとか、どこで何をやっていたかが書いてありました。養親のほうもどういう家で何をしているから問題なさそうだ、じゃあゴーサイン!みたいなこと。
阿久津

書きぶりは調査員によるので、それはけっこう内容がある文章を書いてくれていますね。無味乾燥に淡々としか書いていないものもあるので。
ryuki

魚屋でアルバイトとかね(笑)
志村

その調査官の主観なんですね。何を残すかって決まってるんですか?ちゃんとフォーマットみたいなのあるんですか?
阿久津

私もいろいろな書類を見せていただいてますけど、決まったフォーマットはないと思います。その後、乳児院や児童養護施設へ入って、そこから養子に行く子も多く、その場合は児童相談所が持ってる記録のほうが情報が多いということもあります。また、一人の当事者の記録が戸籍とか裁判の審判書とか、いろんなところに分散されているため、一つの窓口に申請すれば全ての情報が入手できるようにはなっていない現状も問題です。ひとつひとつ自分で手続きしないといけないですし、民間の機関などでは申請しても見せてくれなかったり、管理していませんと言ってくるところもあるのです。時間が経過するともう見られないということもあるので、早く動ければ情報量は増えるでしょう。
志村

でも自分の意思で申請するとしたらどんなに早くても16歳頃ですよね。それ以前は養親が協力的じゃないと……裁判所の調査報告書の保管期限は5年ですよね?
参考 特別養子縁組審判の記録
阿久津

そうですね、5歳では何もできないですね。
ryuki

25年はほしくないですか、やっぱり。
志村

30年ぐらいがいいんじゃないかな。成人してからもまだ余裕があってほしい。
阿久津

養親さんからも要望が出るので、養子縁組が成立した時点であっせん団体から「早めに取っておいてください」っていう声掛けもあるようです。調査報告書自体の保管期間を簡単に伸ばすことはできないので。
志村

その機会を逃したあと、子育てで一番大変な時期の5年以内にっていうのは厳しいですよね。
ISSJ職員
審判書は確定するタイミングで養親さんには送付されますけど、調査報告書はご自身で請求しないと取れません。私たちからも、調査記録に生み親さんの容姿とか、そのときの様子、例えば涙を流していたとか、そういう心情的なことを盛り込んでもらえないかと調査官に頼むこともあるのですが。
志村

それはその担当者のセンスが問われますね。これはけっこうガチャだよね。
阿久津

あとは皆さんもご存知とは思いますが、あっせん団体が一番当時の記録を持っていたりします。私は8年前に全国のあっせん団体を回って調査をしたのですが、ある団体は、生み親さん、養親さん、当事者ごとにファイルを作り、生まれる前のお母さんの記録や生まれたときの写真など入手した全てを保管していました。反対に、紙一枚分の内容しか残していない団体もあり、本当にそれぞれなところが問題だと思います。また、個人でやられている団体は、個人都合で途中で縁組事業を終えてしまうこともありますからね。その時に記録がどこかに引き継がれないと、もう辿る術が無くなってしまいます。最後にどこか、セーフティネットみたいな記録を預かってくれるようなシステムがあるといいのですが。
志村

仕事だって普通にデータバックアップ取るじゃないですか。データで保存するのって難しいんですかね。火事になったらどうするんだろう。
阿久津

「火事でもうちの金庫は燃えないんです」っていうある団体に私が伺ったとき、空いていたんです。金庫の扉が。
志村

わ~これ燃える以前の問題ですよね。でも子どもの立場からすると、その保存に対するその熱量の差が「運任せ」でいいんですか?って思ってしまいますよ。
阿久津

全くその通りです。運が良ければ全部ありますみたいな現状で。
志村

じゃぁそういうことに左右されないのは審判書だけですか?
阿久津

まあそうですね。唯一全員が手に入れられる基本情報は審判書と、場合によっては児相の記録。
参考 記録にアクセスするには
志村

審判書って何が書いてあるんですか?
参考 特別養子縁組審判の記録
阿久津

氏名のほか、事案の概要、養子縁組を審判した理由と結果が記載されているのですが、それもばらつきがあります。書く人によるので。
志村

で、よって養子とする、みたいなそんな感じですか?
ISSJ職員
でもそれも後で請求すると黒塗りされている箇所があったりするので平等ではないです。多分本当に平等なのは戸籍。
参考 戸籍謄本とは?
阿久津

唯一の。戸籍は当事者なら誰でも取れますしね。
裁判所のほうももうちょっと重要さを理解していただいて、調査報告書の保管期間を30年くらいまで引き上げて、戸籍のように平等に手に入れられる状況を作るべきですよね。今だと本当に運任せが過ぎる感じになっているんですよ。
志村

よかったね、ryuki君は。
ryuki

最強(笑)。ゲームの課金キャラじゃないけど、何でも持ってる。
志村

調査報告書は生みの親に会ったときにどれぐらい違ってたりするのかすり合わせることもできるね。
ryuki

魚屋でアルバイトしてたんじゃなかったらどうしよう(笑)でも、これ以上何を知りたいかもわかんないですよね。
みぞぎ

僕は戸籍をとって、その後児相に情報開示請求をしたら、諸々まるっと送られてきました。審判書、遺棄事件として扱われたので当時の新聞三社分の記事のコピー、あと児相の記録ですね。私が保護されたタイミングから、いつ病院に行ったとか、検査で異常がなかったとか。どこの乳児院に連絡して入所余裕があるかどうかを確認したということまで。乳児院で2歳になった頃、今の養親とのマッチングが始まり、1週間お泊りしたときの様子、何をよく食べて喜んでいるとか、そういう詳細な内容が全部ひとつの書類にまとめられていました。黒塗りは審判書の中だけ少しあったかなぐらいでした。
阿久津

それはかなり良い事例ですね。
みぞぎ

結構言ったんです。開示請求の書類の中に請求理由を書くところがあって、小さい字でたくさん書いたんですけど、それでも電話かかってきたときに「なぜ知りたいのですか?」と聞かれ、「え?書きましたけど?」って。その上「養親さんにちゃんと話してます?」と聞かれて「言ってないです」と答えたんです。うちの親は僕にずっと隠してきたので協力的じゃないだろうなと思っていたこともあるんですが、それよりも「自分の情報を今知りたいと思っているのに、うちの両親が死ぬのを待たないといけないんですか?」って電話口でちょっと怒ったんですよ。情報を出してもらえないのは理解できないって訴えたら、「ちょっと検討します」となり、1ヶ月後ぐらいにどーんと送られてきた。
阿久津

そうだったのですね。
みそぎ

でもかなりもめたらしいです。何回も会議してどの情報を出すかを話し合ったと後日聞きました。
阿久津

その記録は原本のコピーですか?誰かがまとめて打ち直したものですか?
みそぎ

一人の担当者が当時からまとめていたものをコピーしたのだと思います。手書きの同じ筆跡でした。
阿久津

それはちゃんとした書類でしたね。
ISSJ職員
でもその、その交渉の仕方によって対応が変わるということはありますね。
みそぎ

後日談として担当者が「熱意が大事なんですよ」と言ってたのはどうかと思いました。遠方から開示請求書が送られてきて、郵送で返してほしいという人と、現地まで来て窓口で話を聞かせてくださいっていう人を比べたら、熱意が違うから出せる情報の量も変わってくるなんてこと言ってたので。でも多分開示の事例がそこまでないような田舎だったので、経験値がなくて窓口も対応がわからなかったのかなとも思いましたけど。地方の児相同士が連携することもできていないですよね。
阿久津

北海道などやれているところもあるのですが、なかなかできていないですね。
ISSJ職員
私たちが児相に問い合わせるときも、「当事者は何を知りたいのですか?」と聞かれて、例えば「実母の健康情報です」と言ったら、先方は健康情報だけを抜粋するんですね。「実母の人柄を知りたいです」っていう場合は、結局その方の主観ベースでの情報が出されることになり、本来であれば開示できないところ以外は全部出してもらっていいものですよね。
阿久津

「何を知りたいんですか?」と聞かれて答えてしまうと、出てくる情報量が狭まる可能性は大きいですね。
ryuki

とりあえず手当たり次第聞くんですかね。
志村

それが嫌ならやっぱり情報の一元管理する所を作るべきですよね。で、その窓口は僕たち(当事者)がした方がいいと思います。だって同じ当事者なんで、相談を受けたときに「いやこれはまだ知らない方がいいんじゃないですか」とかアドバイスもできるし。
阿久津

年齢によってはまだ知らない方がいい情報があると感じます?
志村

年齢だけじゃないと思います。例えば性暴力とか、生み親の年齢が若過ぎるとか、事情を知ってショックを受けることもありますからね。
みそぎ

僕は知るべきだと思う。傷つくのは乗り越えていく過程の入り口なので、僕はたとえ相手が小学生でもどうしても知りたいと迫られた場合は言っていいと思うタイプです。
それを支えるために養親さんはいるんだから、傷つかないようにと隠されるのは嫌です。いくつになっても傷つくことはあるんで、大切なのはそこから先だと思うんですよね。
志村

どう思われます?性暴力があったんですよって言われるわけですよ
ryuki

僕は小さい頃から養子だよっていう話をされてましたけど、16歳の時にもっと知りたいっておやじ(養父)に言ったんですよ。そしたら出自に関することとして、本当の父親は妊娠がわかって逃げたということ、わが家は子どもができなくてお母さん(養母)がとても悲しい想いをしていたこと、っていうのをあらたまって聞かされたんです。で、僕の中の最後の空白だった部分を埋めてもらったような気持ちになりましたね。
志村

なんか出自に関する記録を100項目ぐらい分けて、ボタンを押すとオープンって見られるみたいにしたらいいんじゃないかな。
阿久津

確かに、段階的に知ることもできますしね。
志村

100個みたい人は100個のボタンを全部押せばいいんで。
みそぎ

項目を全表示した上で知りたい内容そこから選べるっていうのが一番いいね。
志村

それはいいですね。行政はこういう記録の残し方してこなかったですもんね。
お話を聞いて
ryukiさんたちは遺伝子検査にも興味があり、将来的に調べてみたいと思っているそうです。
実の両親のもとに産まれていれば、出生時の様子を知りたくなれば目の前にいる親や親族に気軽に聞けます。自分のことだけでなく、親の性格を子どもはふつうにわかって成長するし、病歴を知ることも可能です。この当たり前のことが、彼ら養子当事者にとっては決して当たり前ではなく、様々な手を尽くさない限り、知りたい情報を得ることはできません。例えば、図書館に行って窓口で検索してもらえば、すぐに希望の本が借りられるような、このくらいスムーズに情報を引き出すことができるようになれば、どんなにか心配事も軽減できるでしょう。
解決できるまでにはまだかなりの時間がかかるかもしれません。けれど、YouTubeを立ち上げて積極的に発信している彼らの活動を見ていると、「それでも声をあげていく」ということがいかに大切かを実感させられます。
(ライターW)
Originのみなさん、阿久津先生ありがとうございました。
養子縁組の記録について、ISSJに寄せられる相談や情報をもとにウェブサイトを作成しました。
ルーツ探しについて、疑問に思ったり、尋ねてみたいことがあれば、お気軽に相談窓口にお問合せください。
このページは「養子縁組後の支援の強化」として、日本財団の助成を受けて作成しています

