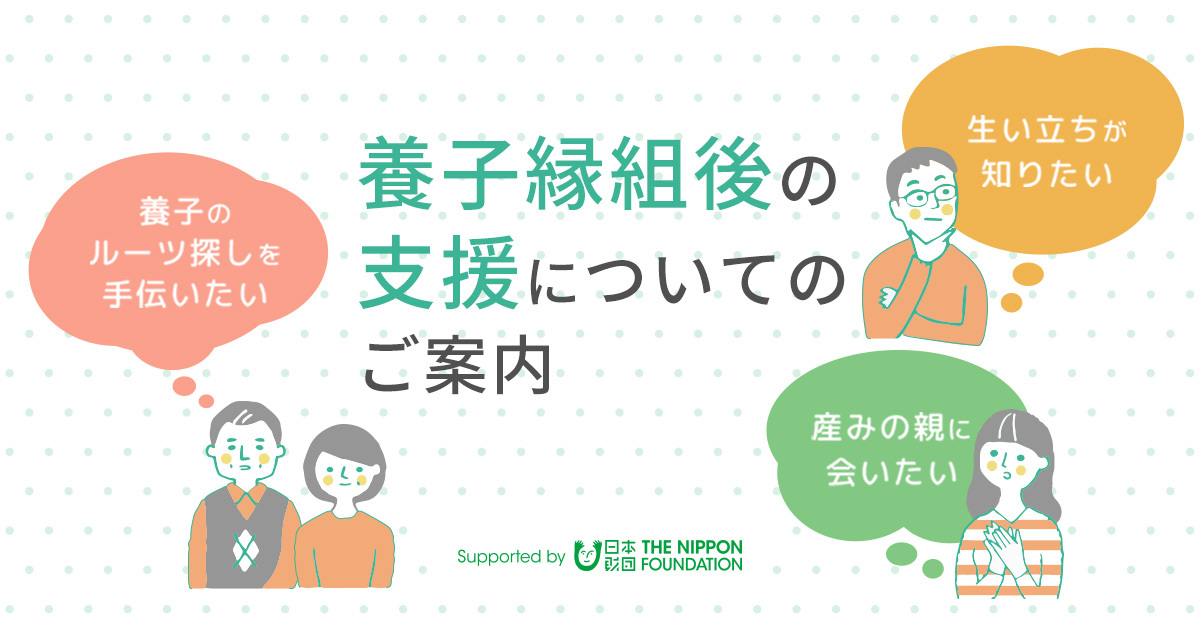現在、養子縁組のあっせんを行うのは、全国の児童相談所および「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」(養子縁組あっせん法)に基づく許可を受けた民間あっせん機関(民間あっせん事業所)です。
児童相談所(行政機関)
児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置された行政機関です。原則18歳未満の子どもに関する相談・通告に、児童福祉司・児童心理士など専門スタッフが応じます。子どもの発達や養育に関する相談、一時的保護、里親委託、乳児院、児童養護施設などへの入所や養子縁組を支援するなどの機能があります。
参考リンク
民間のあっせん機関など
民間あっせん機関
2018年4月に「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」(養子縁組あっせん法)が施行されました。それ以前は、第二種社会福祉事業の届出により、養子縁組のあっせん事業を行うことができましたが、養子縁組あっせんにより、都道府県の許可が必要になりました。2024年4月1日現在、全国で22の事業所が許可を受けています。
廃業したあっせん事業者
養子縁組をあっせんしていた事業者が廃業すると、養子当事者が当時の記録について請求や問い合わせをする先がなくなってしまいます。養子縁組あっせん法は、民間あっせん機関が廃業する際に、養子縁組に関する記録を都道府県または他の許可を受けたあっせん機関に引き継ぐことを義務付けています。しかし、同法施行前に廃業した事業者の中には、記録を廃棄してしまったケースもあります。
特別養子縁組ができるまで
1987年に特別養子縁組が制定される以前は、すべて「普通養子縁組」でした。普通養子縁組においては、生みの親と養子との法的な親子関係は存続するため、養子は生みの親の戸籍証明を請求し、生みの親の住所や世帯を知ることができます。
また、特別養子縁組が制定される以前は、「藁の上からの養子」(生まれて間もない他人の子どもを自分の子どもとして出生届を出して育てること)という慣行も一部で見られました。
参考リンク 日本財団子どもたちに家庭をプロジェクト「4月4日養子の日 すべては赤ちゃんの命を救うために 産婦人科医・菊田昇医師の妻・菊田静江さんインタビュー」
関連するページ


困ったとき、不安に思ったときはお気軽にご相談ください